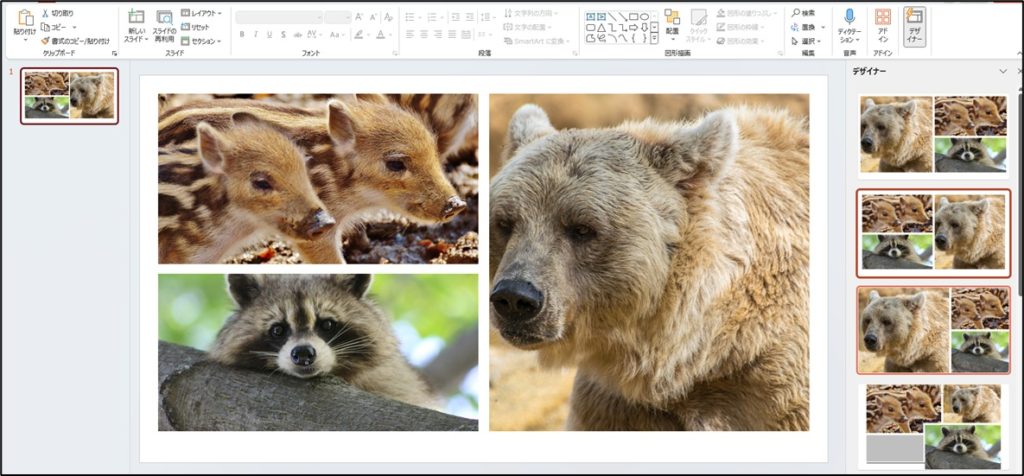2024年12月25日
2024年忘年会
こんにちは、N.Mです。
弊社の活動記録も本投稿が2024年最後の更新となります。
内容はタイトル通り忘年会となってますが、「楽しかったです!」で終わりそうなので
もう少し内容のあるものをお届けできたらと思います。
去る2024年12月13日、弊社帰社日にて業務報告会の後、忘年会が行われました。
・・・ここで「帰社日」という単語が出てきましたのでご説明しましょう。
<帰社日とは?>
読んで字のごとく会社に帰還する日となり、
SES事業を営む企業で帰社日を設けてる会社は多いというか基本あります。
今となってはリモート勤務の方もいますが、我々は基本的にお客様先で業務を行っております。
各地に散らばった弊社の戦士たちが一堂に会する日、それが帰社日です。
弊社では第3もしくは第4金曜日が帰社日になることが多く
みんなで事務所に集まり、社内連絡事項の共有や
各々が従事している現場での業務内容や抱えている課題等を報告・相談する場となります。
業務報告会が終わると楽しいご飯会があります。
今回はそのご飯会が忘年会となります。
今年の会場は事務所から徒歩数分のところにある「鮪(マグロ)LABO」さんで行われました。

名前の通り、マグロ料理が豊富なお店です。マグロ祭りをしたい人は是非足を運んでみてください。



お腹がおいしいマグロ料理で満たされ、来年への英気を養った我々はお店前で解散。
帰路につく者、二次会の夜に消えていく者と別れますがその辺はいつか語るとしましょう。
さて忘年会の数週間前、
私は後輩に「HPに使う用と皆で共有する用の忘年会の写真をいっぱい撮ってね」と依頼していました。
まぁ20枚くらいあればいいかなと翌週提出してもらった写真を確認・・・200枚くらいあるやんけ
・・・・・・
・・・・・・・・・💡
アルバム作るか!!せっかくいっぱい撮ってもらったし
こうして忘年会アルバム作成が始まりました。
使用したのはOfficeソフトのPowerPoint(以後パワポ)です。
パワポは主にプレゼンテーションに使用するソフトですがデザイナー機能があり
アルバムを作るにはうってつけです。(作り始めてから知ったんですが)
選定した写真をスライドに挿入するだけでデザイン候補を決めてくれたりとまぁ便利!
下図で一例をご紹介します
1.適当に3枚の画像を挿入して(重なってます)
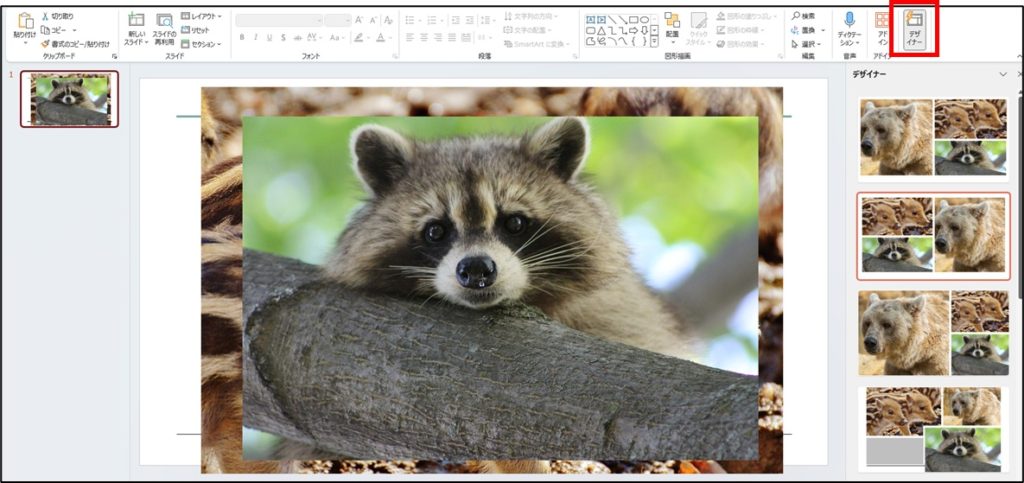
デザイン候補によっては大事な部分をトリミングされたりと注意が必要ですがかなり便利な機能ですね
いつからこんな機能付いたんでしょうね(※PowerPoint2016からの機能みたいです)
便利な機能を駆使してもそこそこ作成時間は要しましたが楽しい作業でした。
今年も残りわずかですがしっかりと今年の仕事を納めてしっかり休み、来年に備えます。
今後の弊社の活動記録もお楽しみに。
2024年12月5日
【資格合格体験記 第5回】
ビジネス統計スペシャリスト エクセル分析スペシャリスト編
こんにちは、入社1年目R.Wです。
今回は前回「ITIL4 ファンデーション編」でお伝えさせていただいた通り、
「ビジネス統計スペシャリスト エクセル分析スペシャリスト」についてお話をさせて頂きます。
<取得した資格を教えてください。>
ビジネス統計スペシャリスト エクセル分析スペシャリスト
<どんな資格ですか?>
「ビジネス統計スペシャリスト」はExcelと統計学の知識を用いた実践的なデータ分析能力を測る資格です。
類似した資格に「統計検定」というものがありますが、ビジネス統計スペシャリストはより実際の実務に特化したものになります。
Excel操作では「データ分析機能」や「Excel関数」「グラフ作成」などの様々なExcelの機能を活用するため、データ分析能力以外にも、Excelスキルを身に付けることが出来ます。
資格の種類は、エクセル分析ベーシック(基礎)とエクセル分析スペシャリスト(上級)があります。
Excelの操作や統計学に全く触れたことがなく不安だという方は、基礎レベルの「エクセル分析ベーシック」から初めても良いと思います。
<受験した理由は?>
次期案件が金融系だということで、データ分析の能力が活かせるのではと考えたのと、
ExcelVBAとExcelをフルに活用する案件だったのでExcelのスキルを向上させたかったからです。
<どれくらい勉強しました?>
140~160時間
<勉強方法について教えてください。>
使用教材:「Excelで学ぶ実践ビジネスデータ分析 ビジネス統計スペシャリスト・エクセル分析スペシャリスト対応」

このテキストを読みこみながら、実際にExcelを操作しながら覚えました。
テキスト以外にアオテンストアという書籍やオンライン問題集などを購入できるサイトで、動画のレクチャーと模擬テストを購入し、学習を進めました。
動画のレクチャーは1万円ほどしますし、上記のテキストの内容を説明しているものになるので、テキストだけで自力で学習を進める方は不要だと思います。
効率的に進めたい方やテキストでは分かりずらい方にはお勧めです。
模擬テストは実際のテスト同様に、Excelを操作しておこなえるので試験前の仕上げとして最適かと思います。
<試験本番について教えてください。>
試験会場はパソコン教室などで受験出来ますので、自宅から30分~40分ほどのところにあるパソコン教室で受験しました。
試験日当日の朝は模擬テストの反復をし、試験会場までの道中は計算方法や用語などをメモにまとめて読み返しました。
実際にExcelで操作するため通常の試験より時間もかかり、Excelを表示させるまでにタイムラグがあったりするので、それでも焦らずに受験が出来るくらい学習を煮詰めた方が安心して受験できると感じました。
試験終了後は、画面に結果が表示されます。
試験対策を万全にしていたので問題なく、一発合格でした。
<合格後の感想は?>
データ分析能力は様々なところで活かせると感じました。
例えば、会社を運営していく中で競合との関係性や従業員の離職理由といったものに対しても、数値で明確な原因などを表すことができますし、
複数の取引先があった場合に、ただ単に金額などではなく、どの取引先が最も自社に利益を生んでいるかなどをその他の要因も含めて算出することが出来ます。
今回は前回とはまた違った資格についてご紹介させていただきましたが、まだまだご紹介したい資格があります。
今後もさらに資格を取得していく予定です。
その際は、再度ご報告させて頂けたらと思いますので、よろしくお願いします。
以上、入社1年目のR.Wでした。
2024年11月27日
【資格合格体験記 第4回】ITパスポート編
入社2年目のT.Iです。
前職は同じくIT業界にて金融系システムの開発に携わっていました。
今回は入社時に取得した「ITパスポート」について、
どのように勉強したかや受験時に感じたことなどを掲載させていただきます。
<取得した資格を教えてください。>
ITパスポートです。
<どんな資格ですか?>
ITパスポート、通称Iパスは、ITを利用・活用する全ての社会人・これから社会人となる学生が学んでおくべきITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。
情報処理技術者試験という試験区分の中の1つで、この試験区分の中では最も簡単な試験になっています。
※情報処理技術者試験は、IT パスポート試験、情報セキュリティマネジメント試験、基本(応用)情報技術者試験
および高度試験(IT ストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験、
IT サービスマネージャ試験及びシステム監査技術者試験)で構成されています。
<受験した理由は?>
元々接客業からIT業界へ転職した為、ITの基礎的な知識というものを勉強していませんでした。
なので改めて勉強し直すいい機会だと思い受験を決めました。
<どれくらい勉強しました?>
勉強を始めて大体4週間程度で合格することが出来ました。
平日の勤務時間中のみ学習を行い、土日祝日は勉強しませんでした。
<勉強方法について教えてください。>
下記の参考書をみて用語については勉強しました。
使用教材:イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生のITパスポート教室 (情報処理技術者試験)
著者:栢木 厚

参考書で用語の知識を付けた後は「ITパスポート過去問道場」というサイトの過去問を反復して解きました。
サイトURL:https://www.itpassportsiken.com/ipkakomon.php
基本的に直近3年間の過去問を中心に実施、回答を確認し間違えたところの確認を繰り返し行いました。
<試験本番について教えてください。>
近くのパソコン教室で受験しました。
受験日が日曜日でしたので受験者数はかなり多かった印象です。
問題数は100問、試験時間は120分です。
4択の選択肢をクリックしていく形式のため回答はしやすかったです。
解き終わったら途中退室可能だったので私が受験した時は60分くらいから退出する人がいました。
全部の問題に時間をかけることはできないので問題文をざっと読んですぐ回答できるかを判断し、できなかった問題・解答に自信がない問題を後回しにして最後に改めて時間をとって読み直して解くことを意識しました。
私は大体90分くらいで終わったかなと思います。
試験終了後に自動で採点され、その場で点数が表示されます。
合格基準も事前に連携されているのでその場で合否の判断ができるのはありがたかったです。
<合格後の感想は?>
Iパスを取得して仕事に役に立ったかと言われると微妙なところではありますが、
しっかり学ぶ機会がなかったITの基礎知識を学ぶことが出来たので意味はあったと思います。
IT業界へ足を踏み入れたいけどまず何を勉強したらいいかわからないという方は取得を目指してみてもいいかもしれません。
<今後の抱負>
さらに上のステップである情報セキュリティマネジメント試験や基本情報技術者試験などにも挑戦していこうと思っています。
以上、【資格合格体験記】ITパスポート編でした。
この内容がお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
2024年11月20日【資格合格体験記 第3回】ITIL4 ファンデーション編
はじめまして、入社1年目R.Wです。
今回はITIL4 ファンデーションという資格についてお話をさせて頂きます。
現在、私はIT関連の資格を5つ保有しています。
その中で、ITIL4 ファンデーションをまず紹介しようと考えたのは、
インフラでも開発でも、営業職でも技術職でも関係なく活かせる資格だからです。
以下の内容を読んでいただければ、理由がわかるかと思います。
ちなみに、次回は「ビジネス統計スペシャリスト エクセル分析スペシャリスト」という統計学を用いたアナリストのような少し珍しい資格の紹介をおこないます。
Excelを使用して行うため、Excelの操作と統計学の内容が理解できれば取得可能な資格なので興味がありましたら、そちらの内容も楽しみにして頂ければと思います。
それでは、まずはITIL4 ファンデーションについて本題に入ります。
<取得した資格を教えてください。>
ITIL4 ファンデーション
<どんな資格ですか?>
ITILファンデーションは、ITサービスマネジメント(※1)及びITIL(※2)に関する基礎知識を保有していることを証明する世界共通の認定資格です。
ITILにはバージョンがあり、私が受験したのはバージョン4となります。
ITIL4はITIL3の内容を理解した上で、さらに事業戦略などにも踏み込んだ内容になっているため、
すでに3を取得している方にも参考になる内容となっています。
※1:ITサービスマネジメント(ITSM)とは自社の社員や顧客など、ITサービスの利用者が問題なく快適に利用できるように利用者目線に立ち継続的に改善していく活動全般のことを指します。
※2:ITIL(Infomation Technology Infrastrcuture Library)とはイギリスの政府機関がITサービスマネジメントのベストプラクティスをまとめた書籍群のことです。
<受験した理由は?>
技術を提供するだけではなく、様々な顧客の要望や企業側の考えなど全体を見通す力がなければ、
日進月歩で進化していくIT業界において生存競争に生き残っていけないと感じていたからです。
<どれくらい勉強しました?>
80~100時間ほど
<勉強方法について教えてください。>
使用教材:「IT Service Management教科書 ITIL 4ファンデーション」

このテキストを2~3周ほど読みこみ、重要な箇所を抜き出し反復して覚えました。
ITの用語以外にも、ビジネス用語なども多々出てくるので、理解できない用語が出てきた場合は後回しや言葉で覚えるのではなく、その都度調べて学習していくことで理解が深まります。
テキスト以外では、Udemyというサイトで問題集と動画でレクチャーを受けられるコースを受講しました。テキストなどの文字で覚えるのが苦手な方や、効率よく学習していきたい方はテキストと併用して受講しても良いと思います。
ただしUdemyではコースごとに数千円から数万円かかるものもあるので、お金をかけたくない方はお勧めしません。
<試験本番について教えてください。>
ITILは受験できる会場が決められているので、自宅から30~40分ほどかかる場所にある試験会場で受験しました。
試験会場までの道中はもちろん、試験日当日の朝にも問題集の反復をしました。
会場では、持ち物は基本的にすべてロッカーに入れることになり、ハンカチやティッシュなども厳重にチェックされます。
試験終了後は、画面に結果が表示されます。
合格が表示されたときは、ホッとされる方が多い印象ですね。受験料が約7万円弱と高額なので。
<合格後の感想は?>
自分自身の視野や考え方が広がったと思います。
ちょうど参画していた案件が上流工程から下流工程まで全て行うところで、ITILの知識が活かせました。
要件定義や設計を行うときに、実際に使用するユーザーだったり顧客などの考えも汲み取り、
サービスレベルなども加味して業務にあたることが出来ました。
<今後の抱負>
ITILは上位の資格が多数あり、ITILの要素をさらに深ぼりした専門性が高いものが多いので
自分自身の知見をさらに広げることができる魅力的なものになっています。
ただ今回取得した資格に有効期限はありませんが、上位資格に受験するには3年以内と制限があるため、期間中に受験できるように準備をしなければなりません。
ただ上位資格は必須の研修と試験がセットで行われ、金額も30万円前後とかなりの高額なので慎重に検討していく予定です。
資格をこれから取得しようと考えている方や、すでに資格取得のために学習に励んでおられる方に伝えたいのは、資格取得がゴールではないということです。
弊社は資格取得後は永続的に手当を支給しています。そのため、目先のお金欲しさに資格取得をする方もいるかと思います。
重要なのは資格を取得することで、例えば自分自身の現在の案件だったり会社に対して、
その資格を活かし利益をいかにもたらすことが出来るかをまず考えることです。
そうすることで自分自身のキャリアアップや昇給などにつながり、毎月の資格手当て以上のものを得られることになると考えています。
以上、入社1年目のR.Wでした。
2024年11月13日
【資格合格体験記 第2回】ExcelVBAエキスパート スタンダード編
初めまして、新入社員のK.Sです。
この度は入社後に取得した資格の一つである「ExcelVBAエキスパートスタンダード」について、
勉強方法や受験の所感について掲載させていただきます。
前職はIT業界にてインフラエンジニアとして従事しておりました。
同じ業界といえど職種の違いから本格的にプログラミングを学ぶのは弊社の研修が初めてでしたが、
その研修の手厚さや自己学習が功を奏し、今では未経験だったプログラミングを習得するに至りました。それでは、よろしくお願いいたします。
<取得した資格を教えてください。>
ExcelVBAエキスパートスタンダード
<どんな資格ですか?>
代表的なOfficeソフトであるMicrosoftExcelのマクロ記述能力に重点を置いた資格です。
Excel上での操作はマクロを書くことで自動化でき、
マクロを用いて作成されたシートはユーザーにとって非常に便利なものになるため、
業界を問わず取得が推奨されるべき資格だと個人的には感じております。
また、ExcelVBAはプログラミング言語でもあるため、これを習得することでプログラミングに対する理解も深めることが可能です。
<受験した理由は?>
弊社の研修でプログラミングについて学ぶ際使用された開発言語がExcelVBAだったので、
『内容を頭に定着させたい』という思いと腕試しを兼ねて受験を決めました。
<どれくらい勉強しました?>
2024年の7月末~8月末の1ヶ月の学習で合格しました。
学習自体は平日の勤務時間中のみ行い、休日は一切触れておりません。
<勉強方法について教えてください。>
至ってシンプルな方法を取っております。
具体的には、まず教科書を1周読破して過去問を受験し、正答率をチェックします。
その上で教科書をもう一周読破して過去問を受験し、正答率の上昇を確認します。
このタイミングで正答率が安定して8割以上出せていれば引き続き過去問を受験しますが、
点数が安定しない場合は苦手箇所を教科書を片手に徹底的に学習していきます。
使用教材:VBAエキスパート公式テキスト Excel VBAスタンダード

<試験本番について教えてください。>
本番はとても小さなテスト会場で受験生は私一人でした。
平日だったので空いている会場で落ち着いて受験出来ました。
受験はCBTという方式で、受験会場のパソコンを用いて画面上の問題に回答していきます。
これはIT資格では一般的な方法のようで、私が同年7月に取得したITパスポートも同様でした。
試験内容は選択問題が少なく、関数名を直接記入する問題が多かったので入念に対策した甲斐がありました。
<合格後の感想は?>
合格の場合は、終了後にその場で認定を受けられるので非常にスマートです。
点数も7割が合格基準のところ8割以上取れたので安心しました。
また、人生初のプログラミングに関する資格の取得となったことから、
新しい武器を持ってエンジニアとしての再スタートを切れたような感覚を得られました。
<今後の抱負>
現在は基本情報技術者試験の学習を行っているので、そちらについても合格出来れば幸いです。
また、研修及び待機期間で習得した知識・技術を現場で発揮し、会社に還元していければと思います。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
今後とも精進して参りますので何卒よろしくお願い申し上げます。
2024年11月7日
【資格合格体験記 第1回】AZ-900編
弊社の活動記録、久々の更新です(ヤッタゼ!)
今までの活動記録は各々自由にテーマを決めて掲載していましたが
資格取得者が増えてきましたのでしばらくはタイトル通り【資格合格体験記】として
弊社メンバーが資格試験に合格するまでの道のりを掲載していきます。
弊社の他社にはない強みとして「資格手当の手厚さ」が真っ先に挙げられます。
大抵の企業さんでは資格試験に合格すると一時金として一回限りの手当をもらうというのが一般的。
しかし!!弊社では取得した資格に応じて”毎月”手当が支給されます。
ゲームでいう永続バフです。資格を取れば取るほど毎月のお手当てが増えます。
ちなみに試験に合格した際は受験料も支給されます。
とまぁ自社アピールはほどほどにして本題に入ります。
<取得した資格を教えてください。>
AZ-900です。
<どんな資格ですか?>
Microsoftのクラウドサービス Microsoft Azure(以下Azure)に関する資格です。
Azure全般の基礎知識を理解していることを証明できる資格となっており、入門編の位置付けです。
類似資格として同じクラウドサービスであるAmazon Web Services(以下AWS)の資格があります。
ちなみに弊社でAZ-900を持ってるのは私だけです。
(みんな人気があるAWSの方取るからです)
<受験した理由は?>
従事している現場で元々オンプレで使っていたシステムをAzureに移行する案件があり、
当時Azureに関して全く知識がなかったため、最低限の知識くらい入れておこうと思って受験しました。
<どれくらい勉強しました?>
勉強を始めてから大体4週間後に合格しました。
時間でいうと40~60時間程度だと思います。
<勉強方法について教えてください。>
基本的には以下の参考書を読み、問題集を解きました。
「合格対策 Microsoft認定 AZ-900:Microsoft Azure Fundamentalsテキスト&問題集」
試験が近くなり、参考書の内容を覚えるくらいになったら最後の追い込みとして
Udemyというオンラインサービスを使ってひたすら問題集を解きました。
スマートフォンアプリでも使用でき、試験直前まで見直しできましたね。
<試験本番について教えてください。>
試験会場はとあるパソコン教室で受けました。
試験が終わったらその場で結果が出ますので結構あっさりしてます。
おそらくAWSもそうでしょうが、この手のMicrosoftなど外国がメインの試験ですと
ちょいちょい日本語の翻訳が怪しかったりします。
ですがUdemyの模擬問題もだいぶ日本語が怪しかったので慣れてました。
<合格後の感想は?>
すごい役に立った・・とは言えませんがそこそこ意味はあったと思います。
Azureはサブスクリプション(定額課金)のサービスですので、
毎月の使用料やCPU使用率などのログを取ったりと
Azureを使う人であれば取っても損はしないかなと思います。
<今後の抱負>
いい加減Javaの初級資格くらい取ろうかなーとは思ってます。
以上、【資格合格体験記】AZ-900編 お楽しみいただけましたでしょうか。
次回アップロードをお楽しみに♪
入社6年目N.Mでした。